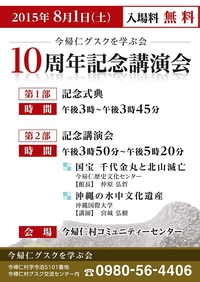2011年11月04日
今帰仁城の発掘成果が新聞トップ記事に
今帰仁城の発掘調査によって新しい発見があり、新聞に大きくとりあげられました。
今帰仁城は1609年薩摩軍の襲来で、焼き討ちにされ、廃城に追い込まれたとされてきました。
今回の発掘調査説明会によると、1600年後半の高級陶磁器が発掘されたことで、薩摩後も今帰仁城内に高官が住んでいた可能性が高くなりました。
高官とは首里城から派遣された監守と考えられ、尚昭威(尚真王の三男)の一族です。城内の一番高いところ、主郭に住んでいたのが、焼き討ちによって城下におりて集落内に住むようになった。とされてきました。
ところが、今回の発掘調査によれば、監守は城内の外郭とよばれる部分に住んでいたわけで、これまでの通説をくつがえす新発見です。
沖縄タイムスより引用 沖縄タイムス10月31日版 (リンクは別ウィンドウで開く、写真も見れます)
発掘現場説明会のとき写真を撮ったのですが、SDメモリカードが壊れてしまい、申し訳ありませんがアップできません。後日現場を撮影してから、写真を投稿します。
今帰仁城は1609年薩摩軍の襲来で、焼き討ちにされ、廃城に追い込まれたとされてきました。
今回の発掘調査説明会によると、1600年後半の高級陶磁器が発掘されたことで、薩摩後も今帰仁城内に高官が住んでいた可能性が高くなりました。
高官とは首里城から派遣された監守と考えられ、尚昭威(尚真王の三男)の一族です。城内の一番高いところ、主郭に住んでいたのが、焼き討ちによって城下におりて集落内に住むようになった。とされてきました。
ところが、今回の発掘調査によれば、監守は城内の外郭とよばれる部分に住んでいたわけで、これまでの通説をくつがえす新発見です。
沖縄タイムスより引用 沖縄タイムス10月31日版 (リンクは別ウィンドウで開く、写真も見れます)
【今帰仁】薩摩侵攻で廃虚化したとされていた今帰仁城跡(今帰仁村今泊)で、その後約半世紀近く身分の高い人物が生活していた痕跡があることが、同村教育委員会の発掘調査で判明した。1609年の薩摩侵攻で同城は焼き払われたとされるが、1600年代半ばのものとみられる陶磁器が大量に出土した。また、これまで不明だった外郭城壁の全体像も、同調査で明らかになった。同村教委は「通説が変わる可能性がある」としており、専門家も「周辺集落の当時の様子を含めて解明していく画期的な発見」と評価した。(浦崎直己)
同城跡の発掘調査は2007年に本格的に始まり、今回は09年以降の発掘調査で外郭西側城壁、建物の基盤となる基壇、炉跡などを確認した。新たに発掘された出土品は、1600年代半ばに制作された肥前陶磁や湧田焼、碁石などの生活雑貨で、貝殻などとともに大量に見つかった。外郭内の東側で確認されていた「基壇建物」とよばれる大規模な石造りの遺跡から出土した。
これらの発掘により、当時としては高価な陶磁や碁石を使う人物が城内で生活し、その住まいの基礎がしっかりした石造りであることなどが推測できる。薩摩侵攻後も同城で身分の高い人が何らかの目的を持って滞在していた可能性があるという。
琉球史が専門の琉球大学の高良倉吉教授は「侵攻後も城が何らかの形で使われていたことは文献で断片的に推測できていたが、その証拠が出土したことは大きな意義がある。磁器などの出土品、外郭城壁の全体像の判明の二つとも画期的な発見だ」と高く評価した。
同村教委文化財係の玉城靖氏は「今帰仁に配置されていた監守が首里に引き揚げた時期とも重なる。従来は集落にいたとされる監守が城内で生活していたのだろう」とみている。
同村教委は今後も、同城跡の発掘調査と整備を進める方針だ。今回発見された遺跡は整備され公開されるほか、出土品の一部は同城跡に隣接する村歴史文化センターで公開する予定。
29日には現地説明会を開き、調査結果を報告。市内外から約70人が参加した。
発掘現場説明会のとき写真を撮ったのですが、SDメモリカードが壊れてしまい、申し訳ありませんがアップできません。後日現場を撮影してから、写真を投稿します。
Posted by usan at 13:29│Comments(0)
│今帰仁城はどんなところ?
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。