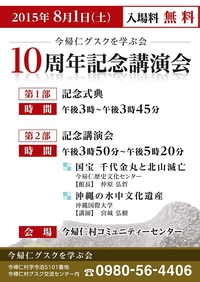2009年08月10日
供のかねノロは、お供したノロ
今帰仁城跡周辺に、3つのノロ殿内(どぅんち)火の神の祠(ほこら)があります。
阿応理屋恵ノロ殿内火の神の祠
今帰仁ノロ殿内火の神の祠
そして、供のかねノロ殿内火の神の祠、の3箇所です。
その1つ、供のかねノロ殿内火の神の祠を訪ねます。
阿応理屋恵ノロ殿内火の神の祠
今帰仁ノロ殿内火の神の祠
そして、供のかねノロ殿内火の神の祠、の3箇所です。
その1つ、供のかねノロ殿内火の神の祠を訪ねます。

供のかねノロ殿内火の神の祠、表示から横道に入る
今帰仁城からハンタ道を数分下ると、右側に表示があります。細い道に入るとすぐに祠(ほこら)があります。

供のかねノロ殿内火の神の祠は、ひっそりと建っている
供のかねノロ殿内火の神の祠は、ややこじんまりした感じで、林の中に建っています。

祠の中には香炉が1つ置かれている
祠の中には、香炉が1つ置かれているだけで、簡素なものです。
供のかねノロはその名のとおり、今帰仁ノロのお供をするノロです。
今帰仁ノロの祠には、3つの香炉がありますが、お供のノロなので1つの香炉なのでしょうか。

案内板には古いかやぶきの屋根の祠の写真がある
案内板には、古いかやぶき屋根の祠の写真があります。建て替えられる前は、このような質素なものだったのですね。
しかし、お供のノロとはいえ、一軒の屋敷を構えていたわけで、やはりノロの地位は高かったのだと理解できます。
ノロ殿内火の神に関するメモ
ノロとは、琉球国の神職で、王国として統一後は首里の王から辞令が出て任命されている。
ノロ殿内はノロどぅんちと読む。殿内とは、身分の高い人、またその屋敷を指す。
火の神はひぬかんと読む。カマドの火の神。屋敷の主が引っ越すとき、祠を建てて火の神を残していく。
Posted by usan at 20:36│Comments(0)
│今帰仁城の周辺案内
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。